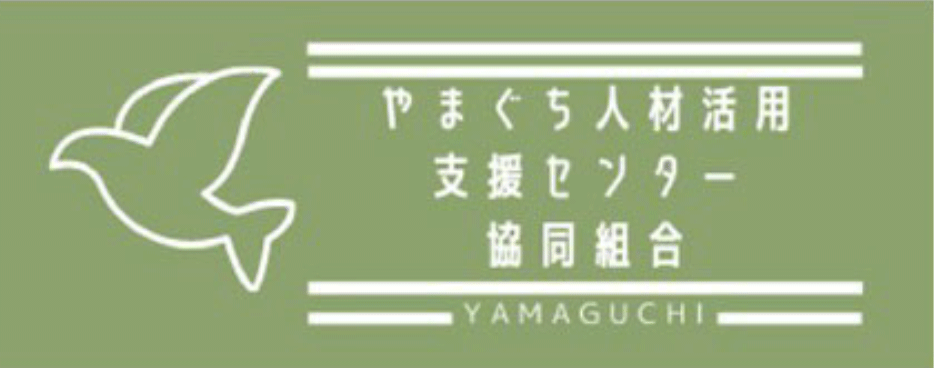【2025年版】M&A業界動向|IT・製造・介護…主要3業界のトレンドと評価ポイントを徹底解説
はじめに:M&A市場の潮流を知り、自社の立ち位置を客観的に把握する
M&Aによる会社の売却を検討する際、自社の強みや弱みを深く理解することはもちろん重要です。しかし、それと同じくらい大切なのが、自社が属する業界全体が、今どのような「風向き」にあるのか、その大きな潮流(トレンド)を客観的に把握することです。
追い風が吹いている業界では、予想以上の高値で、かつスピーディーな売却が実現する可能性があります。逆に、向かい風の業界では、より周到な準備と戦略が求められます。
この記事では、2025年現在の日本におけるM&A市場の全体動向を概観した上で、特にM&Aが活発な「IT業界」「製造業」「介護・ヘルスケア業界」という主要3業界に焦点を当て、それぞれの最新トレンドと、M&Aにおいて高く評価されるポイントを徹底的に解説します。この記事が、M&Aという大海原を航海するための、信頼できる「羅針盤」となれば幸いです。
【全体動向】2025年、日本の中小企業M&A市場の現在地
2025年現在、日本の中小企業M&A市場は、引き続き活況を呈しています。その背景には、主に以下の2つの大きな潮流があります。
後継者不在による「事業承継型M&A」の継続的な増加
日本が抱える最も大きな社会課題の一つである「後継者不足」は、M&A市場を牽引する最大のドライバーです。2025年には、多くの中小企業経営者が引退の平均年齢である70歳を超え、事業の存続をかけた「事業承継型M&A」のニーズは、今後もますます高まっていくことが確実視されています。黒字経営でありながら、後継者がいないために廃業を選択せざるを得ない企業を、M&Aによって救済し、未来へ繋ぐ動きが社会全体で加速しています。
異業種からの参入による「成長戦略型M&A」の活発化
既存事業の成長が鈍化する中、新たな収益の柱を求めて、異業種へM&Aによって参入する「成長戦略型M&A」も非常に活発です。特に、あらゆる産業の基盤となるDX(デジタルトランスフォーメーション)に関連する動きは顕著で、非IT企業がIT企業を買収するケースなどが急増しており、M&A市場全体のダイナミズムを生んでいます。
【業界別動向①】IT業界:技術革新と人材獲得が鍵
動向・トレンド:DX需要を背景に全業種から買いニーズ。SaaS、AI、セキュリティ分野が特に活況。
IT業界は、今最もM&Aが活発な業界の一つです。企業のDX化が経営の最優先課題となる中、優れたITサービスや技術を持つ企業に対しては、同業だけでなく、製造、小売、金融といったあらゆる業界から買いニーズが殺到しています。特に、安定した収益モデルであるSaaS(Software as a Service)、技術革新が著しいAI(人工知能)、そして重要性が増すサイバーセキュリティの3分野は、引き続きM&A市場の主役となっています。
主な買い手の特徴:大手ITベンダー、コンサルティングファーム、事業会社のDX推進部署など。
買い手は、自社のサービスラインナップを拡充したい大手ITベンダーや、戦略だけでなく実行部隊を求めるコンサルティングファーム、そして自社のDXを内製化したいと考える非IT系の事業会社など、非常に多岐にわたります。
高く評価されるポイント:独自の技術・サービス、優秀なエンジニア組織、安定したストック収益。
IT企業のM&Aでは、単純な売上や利益以上に、以下の3点が極めて高く評価される傾向にあります。
- 独自の技術・プロダクト: 他社にはない、模倣困難な技術や、特定の課題を解決する優れたソフトウェア製品。
- 優秀なエンジニア組織: 慢性的なIT人材不足を背景に、優秀なエンジニアが多数在籍し、その定着率が高いことは、それ自体が大きな価値となります。
- 安定したストック収益: SaaSビジネスにおけるARR(年間経常収益)やMRR(月間経常収益)といった、継続的に発生する収益モデルは、事業の安定性を示す指標として高く評価されます。
【業界別動向②】製造業:事業承継とサプライチェーン再編
動向・トレンド:後継者問題が最も深刻な業界の一つ。大手メーカーによるサプライチェーン見直しも活発化。
日本のものづくりを支えてきた製造業は、経営者の高齢化が最も進み、後継者問題が特に深刻な業界です。そのため、事業承継を目的としたM&Aが大多数を占めます。また、近年の国際情勢の不安定化を受け、大手メーカーが部品調達網などのサプライチェーンを国内回帰・再編する動きも活発化しており、その過程で、特定の技術を持つ中小製造業がM&Aの対象となるケースも増えています。
主な買い手の特徴:同業大手、海外企業、プライベートエクイティファンド。
買い手は、国内シェアの拡大や生産能力の増強を目指す同業大手が中心です。また、日本の高い技術力を求めて、海外企業が日本の町工場を買収するケースや、複数の企業を統合して経営効率化を図るプライベートエクイティファンドの動きも目立ちます。
高く評価されるポイント:独自の製造技術・特許、特定の顧客との強固な関係、工場の生産能力・立地。
製造業のM&Aでは、財務諸表に現れない強みが価値の源泉となります。
- 独自の製造技術・特許: 他社には真似できない、ニッチで特殊な加工技術や、取得している特許。
- 特定の顧客との強固な関係: 大手メーカーなど、特定の顧客と長年にわたる安定した取引実績があること。
- 工場の生産能力・立地: 最新の設備や、拡張の余地がある生産能力、そして物流のハブとなるような戦略的な工場の立地。
【業界別動向③】介護・ヘルスケア業界:社会課題解決と規模の追求
動向・トレンド:超高齢化社会による需要増、人材不足、制度改正への対応。規模の経済を求める動きが加速。
超高齢化社会を背景に、介護サービスの需要は拡大し続ける成長産業です。しかしその一方で、深刻な人材不足や、3年ごとに実施される介護報酬改定への対応など、経営上の課題も山積しています。こうした背景から、単独での事業運営に限界を感じ、M&Aによって経営基盤を安定させ、規模の経済を追求する動きが業界全体で加速しています。
主な買い手の特徴:同業大手、異業種(不動産、IT、給食など)。
同業の大手介護事業者が、エリアのシェア拡大や人材確保を目的に小規模な事業所を買収するケースが主流です。また、成長市場への参入を狙い、不動産会社(施設をアセットとして評価)、IT企業(業務効率化システムを提供)、給食会社(食事サービスで連携)など、異業種からの参入が非常に活発なのもこの業界の特徴です。
高く評価されるポイント:事業所の稼働率、有資格者の数と定着率、許認可、施設の立地。
介護業界のM&A評価は極めて独特であり、利益額以上に、以下の点が重視されます。
- 事業所の稼働率: 施設の定員に対して、どれくらいの利用者がいるかを示す稼働率は、収益性を直接的に示す最重要指標です。
- 有資格者の数と定着率: 事業運営に不可欠な介護福祉士やケアマネージャーといった有資格者が何名在籍し、その定着率が高いかどうかが、サービスの質と事業の安定性を担保します。
- 施設の立地と許認可: 人口の多いエリアや、競合の少ない地域に立地していることは大きな強みです。また、運営に必要な許認可が適切に取得されていることは大前提となります。
まとめ:自社の業界特性を理解し、M&A戦略に活かす
ここまで見てきたように、M&Aのトレンドや評価されるポイントは、業界によって大きく異なります。M&Aを成功に導くためには、まず自社が属する業界の大きな潮流を理解し、その中で自社のどのような強みが「価値」として評価されるのかを客観的に分析することが不可欠です。
業界動向は、経済情勢や技術革新、法改正などによって常に変化しています。信頼できるM&Aの専門家から最新の情報を得ながら、自社の強みを最大限にアピールできる、最適なM&A戦略を立てていきましょう。