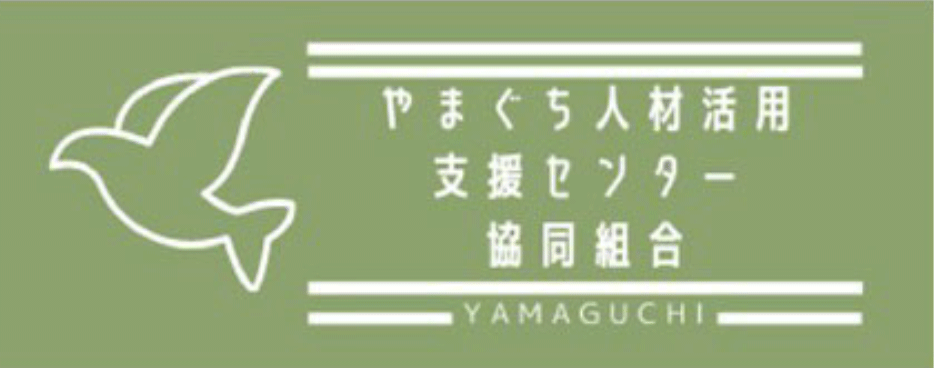【専門家が解説】M&Aの企業価値評価(バリュエーション)とは?3つの計算方法と価格が決まる仕組み
はじめに:「自社の価値」を客観的に知ることが、M&A成功の第一歩
M&Aによる会社の売却を考え始めた経営者の皆様が、最初に、そして最も知りたいと願うこと。それは、「自分の会社は、一体いくらで売れるのだろうか?」という、率直で根源的な問いではないでしょうか。
この問いに、客観的な根拠をもって答えるための専門的なプロセスが「企業価値評価(バリュエーション)」です。
企業価値評価は、M&Aの交渉における全ての出発点となります。自社の価値を客観的に把握していなければ、買い手から提示された価格が妥当なのか判断できず、交渉の主導権を握ることもできません。
「計算方法が難しそう」「専門用語が多くてよく分からない」と感じる方もご安心ください。この記事では、M&Aの専門家である私たちが、経営者の皆様に向けて、企業価値評価の基本的な考え方から、中小企業M&Aで実際に使われる計算方法、そして最終的な売却価格が決まるまでの仕組みを、一つひとつ丁寧に解説していきます。
この記事を読み終える頃には、自社の価値の測り方を理解し、自信を持ってM&Aの第一歩を踏み出せるようになっているはずです。
そもそも企業価値評価(バリュエーション)とは?
なぜM&Aに企業価値評価が必要なのか?
M&Aにおける企業価値評価は、例えるなら「不動産売買における物件査定」のようなものです。売り手と買い手が、お互いに納得できる価格で取引を行うための「客観的な物差し」の役割を果たします。
- 売り手にとって: 自社の価値を理解し、交渉のベースとなる希望価格を設定できる。安く買い叩かれることを防ぐ。
- 買い手にとって: 投資に見合うリターンが得られるか判断するための、合理的な根拠となる。
- 双方にとって: 交渉を円滑に進め、最終的な価格決定における共通の土台となる。
適切な企業価値評価なくして、M&Aの成功はあり得ません。
「企業価値」と「株式価値」、そして最終的な「売却価格」の違いを理解する
ここで、よく混同されがちな3つの「価値」の違いを明確にしておきましょう。これは非常に重要なポイントです。
企業価値(事業価値): 会社全体の価値のこと。会社の事業そのものが将来にわたって生み出すキャッシュフローの総価値であり、株主だけでなく、銀行などの債権者も含めた、全ての資金提供者に対する価値を示します。
株式価値: 売り手である株主の取り分となる価値のこと。計算式はシンプルです。
株式価値 = 企業価値 - 有利子負債など(借入金など)
つまり、会社全体の価値(企業価値)から、銀行などに返済すべき借入金などを差し引いた残りが、株主の手に渡る価値(株式価値)となります。
売却価格(M&A価格): 最終的に売り手と買い手が合意し、実際に取引される価格のこと。株式価値をベースに、買い手との交渉によって決定されます。買い手が、あなたの会社と自社事業との間に大きな相乗効果(シナジー)を見出せば、株式価値を上回る価格で取引されることも珍しくありません。
「企業価値評価で算出されるのはあくまで目安であり、最終的な売却価格は交渉で決まる」ということを、まずは心に留めておいてください。
【図解】企業価値評価の代表的な3つのアプローチ
企業価値を評価する方法は一つではなく、会社の状況や評価の目的に応じて、様々なアプローチが用いられます。大きく分けると、以下の3つのアプローチが存在します。
アプローチ1:コストアプローチ – 会社が「今持っている資産」はいくらか?(時価純資産法)
会社の貸借対照表(B/S)に着目し、「今、会社が解散したらいくら残るか」という観点から価値を評価する方法です。
- 代表的な手法:時価純資産法
- 貸借対照表に記載されている資産を、帳簿上の価格(簿価)ではなく、現在の市場価格(時価)に置き換えて再評価し、そこから負債の時価を差し引いて株主価値を算出します。例えば、土地や建物、有価証券などは、購入時よりも価値が大きく変動している可能性があるため、時価で評価し直します。
- メリット: 客観性が高く、分かりやすい。
- デメリット: 会社の将来の収益性や、ブランド・技術力といった「目に見えない価値」が反映されない。
アプローチ2:インカムアプローチ – 会社が「将来生み出す収益」はいくらか?(DCF法)
会社の「将来性」に着目し、「将来、どれだけのキャッシュフロー(現金)を生み出す力があるか」という観点から価値を評価する方法です。
- 代表的な手法:DCF(Discounted Cash Flow)法
- 会社が将来生み出すと予測されるキャッシュフローを、M&Aのリスクなどを考慮した割引率で現在価値に割り引いて合計し、企業価値を算出します。スタートアップや成長企業など、将来性が重視される会社の評価に適しています。
- メリット: 会社の将来性や独自性を評価に反映できる。
- デメリット: 将来の事業計画の立て方や割引率の設定によって、評価額が大きく変動するため、客観性に欠ける側面がある。
アプローチ3:マーケットアプローチ – 「市場で類似企業」はいくらで評価されているか?(類似会社比較法)
株式市場に着目し、「あなたの会社と似ている上場企業は、市場でどれくらいの価値で評価されているか」という観点から、相対的に価値を評価する方法です。
- 代表的な手法:類似会社比較法(マルチプル法)
- 事業内容や規模が似ている上場企業をいくつか選び出し、それらの企業の株価が利益や純資産の何倍になっているか(株価収益率PERなど)を分析し、その倍率をあなたの会社の利益や純資産に掛け合わせて企業価値を算出します。
- メリット: 市場の評価に基づくため、客観性が高い。
- デメリット: 未上場の中小企業と完全に一致する類似上場企業を見つけるのが難しい。
中小企業M&Aで最もよく使われる評価方法を分かりやすく解説
上記3つのアプローチは理論的なものですが、多くの中小企業のM&Aの現場では、より実務的で分かりやすい評価方法が用いられます。
基本の考え方は「時価純資産 + 営業権(のれん代)」
中小企業のM&Aでは、コストアプローチをベースに、インカムアプローチの考え方を加味した、以下の計算式が広く用いられます。
株式価値 = 時価純資産 + 営業権(のれん代)
これは、会社の「現在の資産価値(時価純資産)」に、ブランド力や技術力といった「目に見えない将来の収益力(営業権・のれん代)」を足し合わせるという、非常に合理的で分かりやすい考え方です。
「のれん代」とは何か?目に見えない価値をどう評価するのか
のれん代(営業権)とは、貸借対照表には載ってこない、会社の無形の価値、つまり「将来の収益力」のことです。具体的には、以下のようなものが含まれます。
- 長年かけて築き上げたブランドや信用力
- 独自の技術やノウハウ、特許
- 安定した顧客基盤や取引先とのネットワーク
- 優秀な従業員や組織風土
これらの無形資産が、会社の将来の利益の源泉となるため、純資産に上乗せして評価されるのです。
のれん代の計算で使われる「EBITDA倍率法」とは?
では、この「のれん代」は具体的にどうやって計算するのでしょうか。そこでよく使われるのが「EBITDA(イービットディーエー)倍率法」です。
EBITDAとは? 簡単に言うと、「会社の本業でのキャッシュを稼ぐ力」を示す指標です。以下の式で簡易的に計算できます。
EBITDA = 営業利益 + 減価償却費
EBITDA倍率法による、のれん代の計算 このEBITDAを基準に、のれん代を算出します。
のれん代 = EBITDA × 倍率(マルチプル)
この「倍率」は、業種や会社の規模、安定性などによって変動しますが、中小企業M&Aでは一般的に3倍~5倍程度が目安とされています。
【計算例】
- 時価純資産:1億円
- EBITDA(営業利益+減価償却費):3,000万円
- 倍率:4倍
のれん代 = 3,000万円 × 4倍 = 1億2,000万円 株式価値(目安) = 1億円 + 1億2,000万円 = 2億2,000万円
このように、自社のEBITDAを把握することで、のれん代、ひいては会社全体の価値の目安を掴むことができます。
企業価値評価を高めるために、今から経営者ができること(企業磨き上げ)
企業価値は固定的なものではありません。M&Aを検討し始めた段階から、買い手にとってより魅力的な会社にするための「企業磨き上げ」を行うことで、評価額を高めることが可能です。
本業の収益性を改善し、EBITDAを高める
最も直接的で効果的なのは、本業の収益力を高めることです。EBITDAが増えれば、それに連動してのれん代も増加します。不採算部門の見直し、コスト削減、販売促進など、地道な経営努力が企業価値向上に直結します。
不要な資産を整理し、財務をスリムにする
経営者の個人的な資産(高級車、ゴルフ会員権、生命保険など)が会社の経費になっていたり、事業に使われていない不動産(遊休不動産)を保有していたりする場合、これらを整理することで財務状況が改善し、買い手に良い印象を与えます。会社の資産と経営者個人の資産を明確に分離することが重要です。
目に見えない価値(無形資産)を客観的な資料として「見える化」する
自社が持つ優れた技術、独自のノウハウ、強固な顧客リスト、許認可などを、誰が見ても分かるように資料として整理しておきましょう。「我が社の強みはこれです」と客観的なデータで示すことができれば、買い手は安心して高いのれん代を評価しやすくなります。
企業価値評価に関するよくある誤解と注意点
誤解1:「評価額=売却価格」ではないという事実
最も重要な注意点です。ここまで解説してきた評価額は、あくまで「理論上の目安」に過ぎません。最終的な売却価格は、買い手があなたの会社にどれだけの魅力を感じ、将来どれだけのシナジーを見出すかという「期待値」と、当事者間の「交渉」によって決まります。
誤解2:評価額は、評価する専門家や目的によって変動する
企業価値評価は、どの評価方法を重視するか、どのような将来予測を立てるかによって、算出する専門家ごとに結果が異なる場合があります。複数の意見を聞くことも有益ですが、重要なのは、その評価額がどのような根拠で算出されたのかを、自身でしっかり理解することです。
注意点:最終価格は、買い手とのシナジーと当事者間の交渉で決まる
最終的には、買い手候補との交渉力が価格を左右します。自社の強みを的確にアピールし、相手が提示する買収ロジックを理解した上で、信頼できるM&Aアドバイザーと共に交渉に臨むことが、満足のいくM&Aを実現するための鍵となります。
まとめ:客観的な企業価値を知り、自信を持ってM&Aの交渉に臨むために
今回は、M&Aにおける企業価値評価の基本について解説しました。「自社の価値はいくらなのか」という問いへの答えは、単一の絶対的な数字ではなく、「時価純資産に、EBITDAの数年分ののれん代を上乗せしたもの」が、中小企業M&Aにおける一つの目安となります。
しかし、これはあくまでスタートラインです。本当の価値は、あなたの会社の歴史、文化、そして将来性の中に眠っています。
正確な企業価値を把握し、その価値を最大化するためには、やはり経験豊富なM&Aの専門家による客観的な評価と、戦略的なアドバイスが不可欠です。まずはお気軽に専門家へ相談し、自社の価値の現在地を把握することから始めてみてはいかがでしょうか。客観的な物差しを持つことが、M&Aという重要な経営判断を、自信を持って進めるための何よりの力となるはずです。