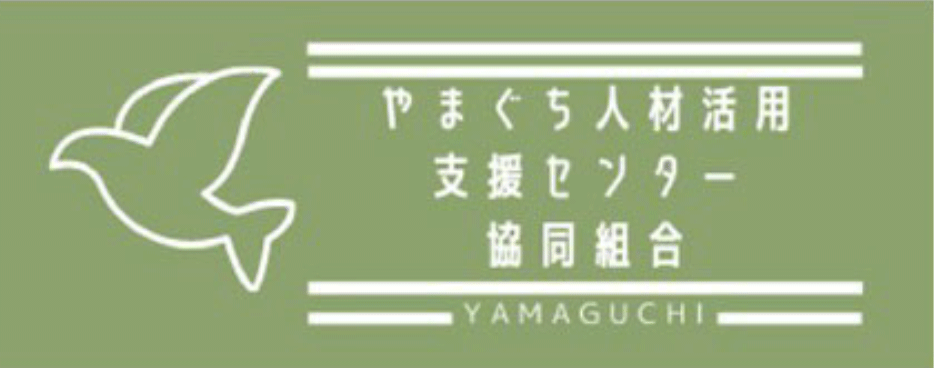【M&Aと税金】会社売却の手取り額がわかる!株式譲渡・事業譲渡の税金計算と節税ポイント
はじめに:M&Aの成功は「最終的な手取り額」で決まる。税金の知識が不可欠な理由
M&Aの交渉において、会社の売却価格は最大の関心事です。しかし、どれほど高い価格で合意できたとしても、その金額がそのまま手元に残るわけではありません。そこから、必ず「税金」が差し引かれます。
M&Aの本当の成功とは、売却価格の額面の大きさではなく、税金を支払った後に、最終的にいくら手元に残ったか、という「手取り額」で測るべきです。そして、この手取り額は、M&Aの手法や少しの工夫によって、大きく変わることがあります。
「税金は複雑で難しい」と敬遠してしまうと、本来得られるはずだった利益を失い、後で「こんなはずではなかった」と後悔することになりかねません。
この記事では、M&Aでかかる税金について、特に中小企業M&Aで代表的な「株式譲渡」と「事業譲渡」のケースを中心に、その計算方法や節税のポイントを、専門家が分かりやすく解説します。正しい税金の知識を身につけ、納得のいく経済的リターンを実現しましょう。
M&Aの税金を理解する大原則|「誰が」「何で儲けたか」で全てが決まる
M&Aの税金は一見複雑ですが、押さえるべき大原則は非常にシンプルです。それは、「誰が(納税者)」、「何で儲けたか(課税対象)」という2つのポイントです。
- 株式譲渡の場合: 株主個人が、株式を売却した利益(譲渡所得)に対して税金を支払います。
- 事業譲渡の場合: 会社(法人)が、事業を売却した利益(事業譲渡益)に対して税金を支払います。
この根本的な違いが、税金の種類や税率、計算方法のすべてを決定づけるのです。
【ケース①:株式譲渡】株主個人にかかる税金
中小企業の事業承継などで最も多く用いられる「株式譲渡」。この場合、税金は比較的シンプルです。
課税されるのは「株主個人」の「譲渡所得」
会社のオーナー経営者のほとんどは、自身が会社の株主です。株式譲渡では、この株主個人が、株式を売って得た利益(譲渡所得)に対して課税されます。
税率は一律「20.315%」!具体的な計算方法とシミュレーション
株式の譲渡所得にかかる税金は「申告分離課税」とされ、給与所得など他の所得とは合算せず、単独で税額を計算します。そして、その税率は所得の金額にかかわらず、一律20.315%です。
- 内訳: 所得税15% + 住民税5% + 復興特別所得税0.315%
計算式は以下の通りです。
税額 = (株式の売却価格 - (株式の取得費 + 譲渡費用)) × 20.315%
【シミュレーション】
- 株式の売却価格:2億円
- 株式の取得費(会社の設立費用など):1,000万円
- 譲渡費用(M&A仲介手数料など):1,000万円
譲渡所得 = 2億円 – (1,000万円 + 1,000万円) = 1億8,000万円 税額 = 1億8,000万円 × 20.315% = 3,656万7,000円 最終的な手取り額 = 2億円 – 1,000万円(譲渡費用) – 3,656万7,000円 = 1億5,343万3,000円
意外な落とし穴!株式の「取得費」が分からない場合の対処法
長年経営してきた会社の場合、「設立時の資本金は分かるが、正確な取得費を証明する書類がない」というケースがよくあります。取得費が不明だと、売却価格のほぼ全額に課税されてしまうのでしょうか?
ご安心ください。その場合、売却価格の5%を「概算取得費」として計上することが認められています。ただし、実際の取得費が5%を上回ることが証明できるのであれば、そちらを使った方が有利になります。
【ケース②:事業譲渡】法人にかかる税金
次に、会社の事業の一部または全部を売却する「事業譲渡」の場合です。こちらは税金の仕組みが大きく異なります。
課税されるのは「法人」の「事業譲渡益」
事業譲渡の主体は会社であるため、売却で得た利益(事業譲渡益)に対して課税されるのは、株主個人ではなく法人です。
税率は「法人税等(約30%~)」+「消費税」!複雑な計算に要注意
法人に課される税金は、主に2種類あります。
- 法人税等: 事業譲渡益は、会社の他の利益と合算され、法人税・法人住民税・事業税が課税されます。この実効税率は、約30%~34%と、株式譲渡の約20%に比べて高くなります。
- 消費税: これが最も大きな違いです。事業譲渡では、譲渡する資産のうち、課税資産に対して消費税(10%)がかかります。
課税資産の例: 建物、機械設備、車両、ソフトウェア、そしてのれん(営業権)など。 非課税資産の例: 土地、有価証券、売掛金などの債権。
なぜ事業譲渡は売り手にとって税金の負担が重くなる傾向にあるのか?
事業譲渡では、法人に約30%~の法人税がかかった上で、その利益をオーナー個人が受け取る際に、さらに配当所得課税や給与所得課税がかかる「二重課税」の状態になりやすいです。また、消費税の納税義務も発生するため、一般的に株式譲渡に比べて売り手の税負担は重くなる傾向にあります。
【一目でわかる比較表】株式譲渡と事業譲渡、税金面での違い
| 比較項目 | 株式譲渡 | 事業譲渡 |
| 納税者 | 株主個人 | 法人 |
| 課税対象 | 株式の譲渡所得 | 事業の譲渡益 |
| 主な税金 | 所得税・住民税など | 法人税等 |
| 税率(目安) | 約20.315% | 約30%~34% |
| 消費税 | かからない | かかる(課税資産に対して) |
M&Aで賢く手取り額を増やすための節税ポイント
M&Aにおいて、合法的な範囲で手取り額を最大化するための代表的なポイントをご紹介します。
ポイント1:役員退職金として受け取る(退職所得控除の活用)
M&Aを機に経営者が引退する場合、譲渡代金の一部を「役員退職金」として会社から受け取る方法があります。役員退職金には、長年の功労に報いるため、「退職所得控除」という非常に有利な税制上の優遇措置があります。
退職所得控除額は勤続年数に応じて大きくなり、控除後の金額のさらに1/2が課税対象となるため、同じ金額を株式の譲渡益として受け取るよりも、税負担を大幅に軽減できる可能性があります。
退職所得控除の計算式
- 勤続20年以下: 40万円 × 勤続年数
- 勤続20年超: 800万円 + 70万円 × (勤続年数 – 20年)
ポイント2:M&Aの手法を慎重に検討する
前述の通り、株式譲渡と事業譲渡では税負担が大きく異なります。自社の状況、そして買い手の意向も踏まえ、M&Aの計画段階からどちらの手法が最適か、税務的な視点からシミュレーションすることが重要です。
M&Aの税金に関する注意点と、専門家への相談
確定申告を忘れずに(申告期限と手続き)
株式譲渡で利益を得た場合、原則として、譲渡した年の翌年2月16日から3月15日までの間に、ご自身で確定申告を行い、納税する必要があります。これを怠ると、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されるため、くれぐれもご注意ください。
M&Aの税務は専門家の領域。なぜ必ず税理士に相談すべきなのか
この記事では基本的な考え方を解説しましたが、M&Aの税務は、個々の会社の状況によって考慮すべき点が無数にあります。特に役員退職金の活用などは、税務署から不相当に高額だと否認されるリスクもあります。
最適なタックスプランニングを行い、税務リスクを回避するためにも、必ずM&Aと税務に精通した税理士に相談してください。
まとめ:正しい税金の知識が、納得のいくM&Aを実現する
M&Aの最終的な成功は、売却価格の大きさだけでなく、税金を支払って手元に残る資金で、あなたがどのような豊かなセカンドライフを送れるかで決まります。
正しい税金の知識は、そのための強力な武器です。M&Aの計画を立てる早い段階から、信頼できるM&Aアドバイザーや税理士と共に、最適なタックスプランニングを検討しましょう。それが、あなたの長年の努力に報いる、納得のいくM&Aを実現するための最も確実な道筋です。